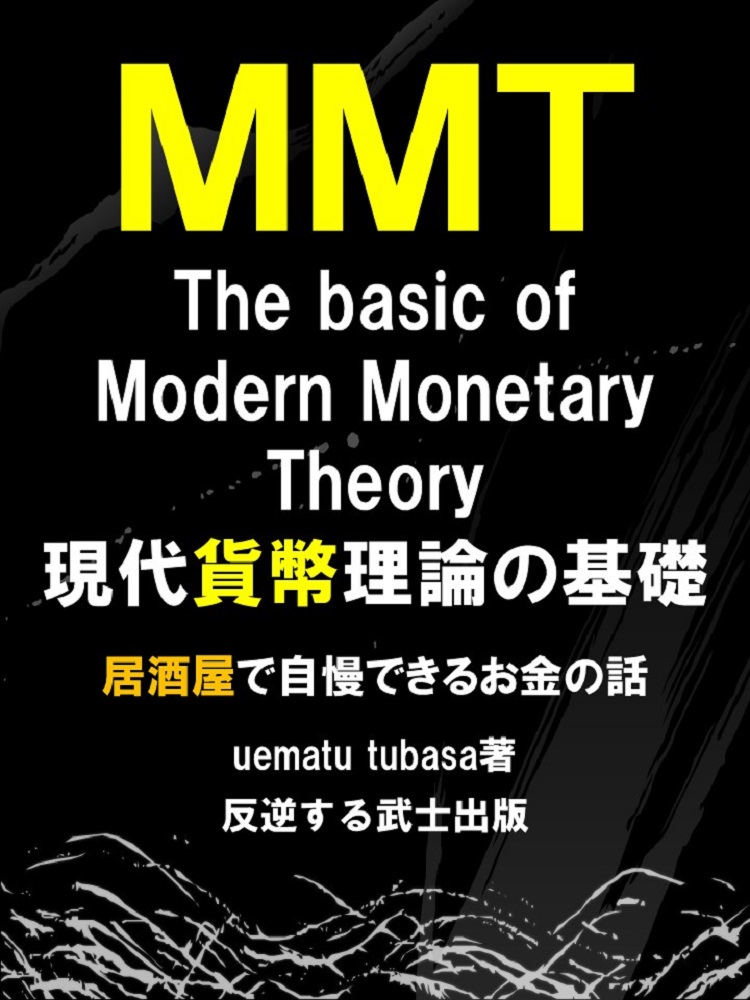
大変お世話になっております。
反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2021年2月16日(令和3年2月16日)
主要通貨と自国通貨は別物である
主要通貨を発行する国は、極端なインフレを招かない限り、どれだけ国債を発行しても行き詰まらない。
引用元:(短評)『MMTは何が間違いなのか?』G・A・エプシュタイン著
だから積極的な財政出動で景気刺激に努めるべきだ。
そんな論法で物議を醸す現代貨幣理論、通称「MMT」の問題点を説く。
上記引用元記事は、G・A・エプシュタイン著『MMTは何が間違いなのか?』という書籍を紹介する記事なのでございますが、現代貨幣理論に関する理解があまりにも的外れ過ぎています。
主要通貨を発行する国に該当する国に適用できる理論ではなく、自国の都合で発行できる通貨を保有している国家に適用できる理論です。
主要通貨とは何なのですか?
極端なインフレを招かない限り、どれだけ国債を発行しても行き詰まらないのではなく、国債発行無しでも政府支出は可能であり、変動相場制を採用して、自国通貨を保有する政府には財政的予算制約は無いという理論です。
だから積極的な財政出動で景気刺激に努めるべきという主張は現代貨幣理論には含まれません。
現代貨幣理論に含まれる政策は就業保証プログラム(JGP)です。
現代貨幣理論に関する理解が根本的に間違ってますよ?
低成長と富の格差を壊すのが現代貨幣理論に基づく積極財政である
(前略)
引用元:魔法のカネのなる木(MMT)という新しい常識と相場の行方
物価と資源の制約を除き、MMT擁護者たちは通貨を「発行している」政府が通貨をいくら使おうと厳密な制限はないと吹聴している。
では、富の格差など、こうした政策で 引き起こされる不均衡についてはどうするのか。
確実に続くことになる低成長についてはどうするのか。
均衡政策についてはどうするのか。
(後略)
『2020年の書「MMT の世界で信仰を探して」』(ジョージ・カラヘリオス)
確かに、中央政府の政府支出には物価制約と資源制約は存在しております。
過度なインフレは低所得者層にダメージを与えるでしょうし、資源の浪費や資源価格の高騰が国民経済全体にダメージを与える可能性がございます。
ただ、現代貨幣理論を支持する政策担当者(例えば、ステファニー・ケルトン)は富の格差などに無関心なわけがありません。
バイデン政権は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、直接給付を行おうとしておりますが、これは確実に所得格差の是正になります。
また、経済成長とはGDPが継続して増えることであり、GDPには政府支出が含まれるのですから、低成長を打開するためにも政府支出の増加が必要なのです。
上記のような低成長対策が無いという批判をする方は、GDPという概念を理解していないのか、経済成長を理解できないのかは存じませんし、場合によっては足し算がわからないということなのかもしれません。
均衡政策というのが、貿易均衡を志向する政策なのか、財政均衡を志向する政策なのかは存じませんが、どちらも無意味であるというのが現代貨幣理論から導ける結論なのです。
財政赤字とは、民間経済にどれほどの貨幣を政府部門が供給したのかという目安であり、それ以上でもそれ以下でもございません。
貨幣の発行主体である中央銀行と中央政府がお金が無いから政府支出できず、貨幣供給が滞るということはあり得ません。
貿易均衡に関しても、ストック・フロー一貫モデルで説明することが可能であり、貿易黒字を目指す必要はありません。
※自国通貨の為替レートが急激に下落したら問題になるかもしれません。
ストック・フロー一貫モデルとは
「ある経済部門(政府部門/民間部門/海外部門)の黒字(赤字)は、その他の部門の赤字(黒字)である。」というものです。
引用元:MMTの源流にして基礎、ゴドリーのSFCモデルとは?
例えば政府が黒字(赤字)である場合は、民間部門と海外部門の合計が赤字(黒字)になります。
経済部門間のフロー(貸し借り)が経済部門のストック(金融資産/金融負債)を積み上げるため、「ストック・フロー一貫モデル」と呼ばれています。
中央政府の財政赤字(政府支出-税収)とは、民間経済から奪わなかったお金ということになりますから、財政赤字が拡大するということは民間経済にとって望ましいことなのです。
もちろん、過度な物価上昇(インフレ)には注意しなければなりませんが、財政赤字こそが民間黒字であり、それこそが常態であるという認識を持たなければなりません。
ここで海外部門の収支にも触れられており、為替レートの変動に関係はしますが、海外部門の赤字(貿易黒字)を確保するという必要性は留意されません。
貿易黒字が他国から貨幣を奪い取ったから勝利であり、貿易赤字が貨幣を奪われたから敗北という時代錯誤的な感覚を捨て去るべきです。
※重商主義という遺物は捨て去りましょう。
海外部門の収支は為替レートに関係するだけであり、よほど極端に為替レートが変動してしまうリスクにだけ留意すればいいだけです。
自国都合で貨幣を発行できるのであれば、海外勢にお金を奪われてしまうことでお金が足りず、政府支出できないということにはなりません。
税金徴収と国債発行が同じ?
それがMMTでは、税金で財源を作るのも、国債で財源を作るのも質的に何ら差がないということになった。
引用元:資本主義にいかに倫理を導入するか――中谷 巌(「不識塾」塾長)【佐藤優の頂上対決】
必要な時が来れば国家権力を持つ政府がいつでも国民からお金を徴収できる。
だから財政赤字になっても、まったく問題がないと考える。
上記引用元記事において、中谷巌という経済学者が発言しているのですが、話になりません。
税金で財源を作るのも国債で財源を作るのも質的に何ら差がないということにはなりません。
日本国民の消費を冷え込ます消費税で税金を徴収することと、国債を発行することが同じわけがありません。
消費税という概念を理解できていないようです。
しかも、現代貨幣理論は税金無しでも政府支出が可能であり、租税が貨幣を駆動すると主張しているのです。
パラレルワールドの現代貨幣理論を主張されては困ります。
租税が貨幣を駆動する
政府は、政府自身が発行した貨幣で租税の支払いを受けると約束。
引用元:【粂博之の経済ノート】財政規律を「神話」と説く現代貨幣理論(MMT)の理屈
国民は納税しないと罰せられるので貨幣を欲する。
商品の対価や給料として貨幣を要求するのも納税手段を得るためで、その結果、貨幣は広く流通する-という理屈だ。
中央政府は納税の義務を国民に課し、法定通貨を納付するように要求するので、国民には貨幣を手に入れるインセンティブが働きます。
その結果、貨幣価値を国民が認識するようになり、民間経済において流通するようになります。
ある意味、国家権力が背景にある貨幣理論であり、なぜ貨幣(特に紙幣など物質的な価値が低いもの)に価値があると認識して、取引の媒体として浸透していくのかという貨幣理論なのです。
国家権力をとにかく毛嫌いするような左翼様にはちょっと気分悪いですよね(笑)。
国家権力の暴走は警戒しつつも、国内の治安維持や対外的脅威に対する防衛を考えれば、国家権力の存在は認めるべきなので、私は租税貨幣論を支持しますし、日本を無税国家にするべきではないと考えます。
以上です。