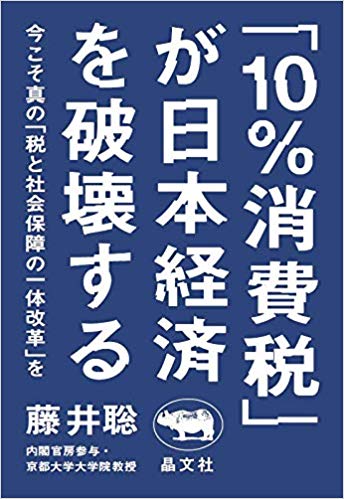
大変お世話になっております。
反逆する武士
uematu tubasaです。
初回投稿日時:2019年9月30日(令和元年9月30日)
【近況報告】地獄の9月が終わります。
10月は様々なイベントがございますが、それを乗り切りつつ、体を休めたいと思います。
消費税は消費行動への罰金である
そもそも消費税とは「消費の抑制」を政策目的とした税制です。
したがって、消費税を導入したり、消費税率の引き上げを行ったりした場合には消費の減退が発生します。
現在、我が国日本はデフレ状態です。
需要と供給を比較した場合、需要が供給よりも少ない状態です。
物やサービスが売れ残ってしまっている状態で消費が減退したら、民間企業の売上がますます減ってしまいます。
確実に景気の悪化を招きます。常識的に考えれば当たり前のことです。
消費増税による消費の減退がどれほど恐ろしいことなのかを理解していただくために、GDP(国内総生産)という経済指標について簡潔に説明したいと思います。
GDPとはGross Domestic Productの略で、一定期間内に国内で生産された付加価値の合計のことです。
セブンイレブンの「和風ツナマヨネーズ」の例で説明します。
日本国内において、生産される物やサービスが「和風ツナマヨネーズ」だけと仮定します。
1個100円として、1年間で1000億個を売り上げたとします。日本のGDPは10兆円となります。
また、GDPには三面等価の原則というものがございます。
三面等価の原則とは「一定期間内に国内で生産された付加価値と総所得と総支出は等しくなる」という原則です。
国内総生産と国内総所得と国内総支出は等しくなるのです。
これも少々難しいお話ですので「和風ツナマヨネーズ」を例として説明します。日本国内において「和風ツナマヨネーズ」が生産されたということはそれを販売して所得を得たということでもあります。
また、消費者は「和風ツナマヨネーズ」を購入しましたので、お金を購入代金として支出したことにもなります。
したがって、物やサービスが消費された場合には、生産と所得と支出が同じ金額だけ行われるわけです。
GDP(国内総生産)という経済指標は国家経済全体の大きさを測るために極めて重要なのです。
本書において、GDPが継続的に増えることを経済成長と定義します。
経済成長が鈍化する、もしくは経済成長できない場合を景気悪化と定義します。
デフレ経済下において、消費税の導入や消費税率の引き上げは経済成長を阻害し、景気悪化を招きます。
簡単な理屈です。
GDPは支出面で考えると一番わかりやすいと思います。
GDPの支出面の内訳は民間最終消費支出と民間設備投資と民間住宅投資と公共投資と政府最終消費支出と純輸出(または純輸入)となります。
GDPの支出面を正確に記載すると民間設備投資と民間住宅投資と公共投資をまとめて総固定資本形成となります。
また、在庫品増加も含めます。
しかしながら、わかりやすさのために総固定資本形成の内訳で定義しました。
また、在庫品増加は統計上微々たるものなので省いて紹介されることが多いようですので省略しました)
我が国日本のGDPの内訳を見てみるとGDPの約6割が民間最終消費支出なのです。
その6割を占める民間最終消費支出を抑制してしまうのです。
金額にすると約300兆円になります。
影響力が想像を絶するぐらい大きいのだとご理解いただけましたでしょうか。
ただでさえ物やサービスが売れない状態なのに、さらに消費を抑制する消費税が存在しているのです。
そして、2019年10月からは10%への消費税率引き上げという暴挙が実行されてしまいました。
日本経済を食い荒らしたいとしか思えません。
消費税が計算しやすい税率になることの恐怖
以下は、藤井聡氏の「10%消費税」が日本経済を破壊するの書評を一部改変して掲載します。
1、税の顕著性についてわかりやすく説明している。
2、働き方改革による残業代減少が消費を抑制すると言及している。
3、消費増税は経済学的問題ではないと言及している。
1について説明します。
消費税は5%から8%に税率が引き上げられ、10%へさらに引き上げられます。
3%引き上げ時と2%引き上げ時では3%の方が影響が大きいと普通は思います。
しかしながら、消費税率が10%というのは計算しやすいがため、どれほど増税されたかを認識しやすく、日本人の消費行動に大きなブレーキをかけることになるというのです。
確かに、増税された分がわかりにくい場合よりも増税された分がわかりやすい方が、どれくらい節約すればいいのか簡単に計算できます。
そして、そのちょっとした節約を日本人全員がやり始めたら”合成の誤謬”が発生し、国家経済における消費が大きく減少してしまいます。
悪い意味で”塵も積もれば山となる”状態。
これは本当に恐怖ですよ。
2について説明します。
昨今は生産性向上と労働時間の短縮が叫ばれております。
残業代の支給が減少すると、消費が減少してしまうというのです。
これは常識的にご理解いただけることだと思います。
消費とは所得によって決定されます
※かなり大雑把に言えばという留保が付きますが・・・
したがって、所得が減れば、消費が減ります。
それが、日本人全体の所得の減少だったら、なおさら消費は減少します。
誰かの消費は誰かの所得ですから、消費の減少は所得(民間企業の売り上げと言っても差し支えない)を招くことになります。
そこに消費増税という消費抑制インパクトが加わってしまったら、阿鼻叫喚の地獄絵図となりましょう。
3について説明します。
どう考えても消費増税が日本経済において打撃であり、財政健全化から遠のくということが統計的に証明されているわけです。
けれども、経済学者、エコノミスト、政治家、財務官僚は消費増税を叫び、日本経済における”リストカット”を続けようとしているわけです。
したがって、消費増税と財政悪化は経済学的問題ではないと藤井聡氏は主張しています。
これ以上の言及は”ネタバレ”のため控えますが、あまりにも率直な藤井聡氏の意見を158頁から引用します。
つまり、我が国政府の財政悪化の根本原因は、政府関係者が無知で愚かであることなのである。
「10%消費税」が日本経済を破壊する pp158
2019年10月⁻12月期はどれほど消費が冷え込むのか大胆予想する
本記事の最後になりますが、消費増税された後の消費の落ち込みを予想してみたいと思います。
ネット界隈を見ると、2019年10月から12月の四半期において、対前期比で10%以上の消費減退が見込まれるというお話がございます。
私はその意見に対しては懐疑的です。
なぜならば、消費増税対策として、ポイント還元や軽減税率などが実行されるため、ある程度は緩和されるからです。
ただ、軽減税率は食品などが対象ですし、ポイント還元はキャッシュレス決済に対応していないとその恩恵を受けることができません。
したがって、ポイント還元や軽減税率でも緩和できないほどの消費減退は発生するでしょう。
おそらく、対前期比5%の民間最終消費支出の減退は発生するのではないでしょうか。
それに伴い、民間設備投資が減少し、民間住宅投資も減少すると思われるので、どれほどのマイナス成長になるのか想像もできません。
この予想が大幅に外れた場合は謝罪記事を出します。
なぜ予想が外れたのかも自己分析します。
※ただし、ある程度の誤差は許容していただければと存じます。
以上です。